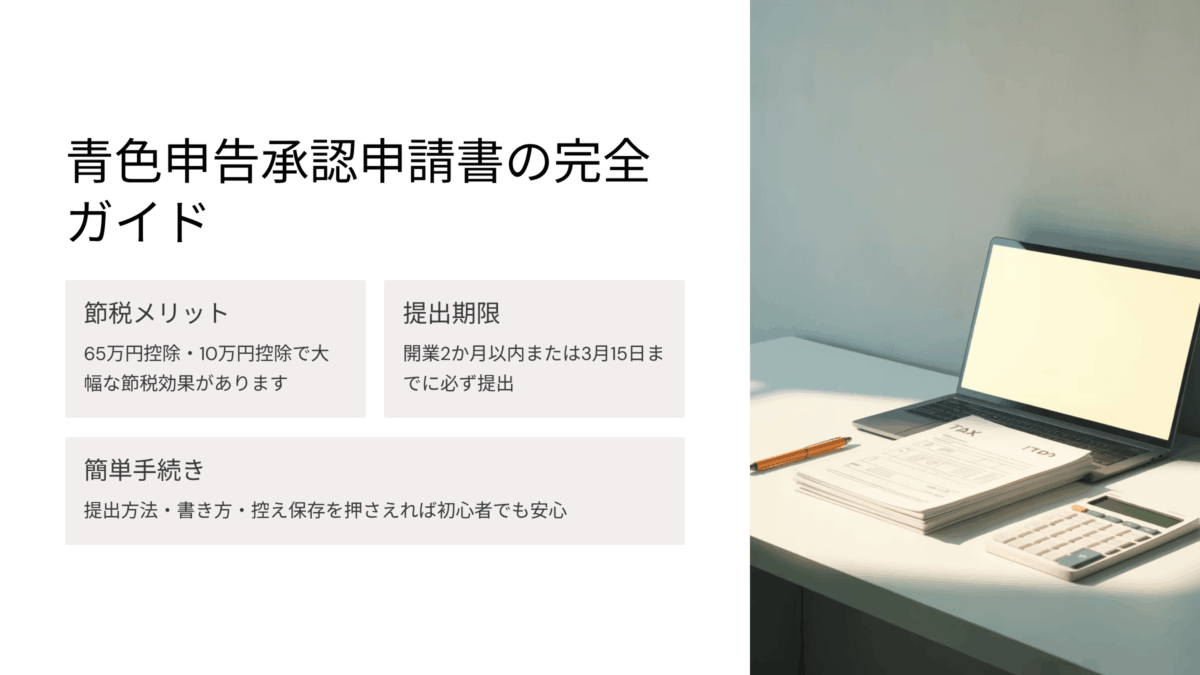「青色申告って聞いたことはあるけど、白色申告との違いがよく分からない…」
「65万円控除や10万円控除って本当に自分に関係あるの?」
「そもそも青色申告承認申請書って、どう書けばいいの?」
もしあなたがそんな疑問や不安を抱えているなら、安心してください。
私も独立した当初、開業届を出したはいいけど、確定申告や帳簿のことなんて全然分からず、税務署に提出期限を聞きに行ってはオロオロしていました。
でも大丈夫。青色申告承認申請書は、書き方の流れや注意点さえ押さえれば、誰でもスムーズに提出できます。しかも、青色申告を選ぶことで 所得税の控除・複式簿記による65万円控除・簡易簿記の10万円控除・記帳義務の整理・不動産所得や事業所得への適用 など、メリットは想像以上に大きいんです。
この記事では、申請書の入手方法から書き方、提出方法、よくある失敗例まで を、私の体験談も交えて分かりやすくまとめました。
きっと読み終える頃には、「自分もできそうだ!」と自信を持って申請できるはずです。
- はじめに:青色申告承認申請書とは何か
- 青色申告制度のメリットと必要性
- いつまでに出すべきか?提出期限のルール
- 国税庁公式様式と最新版の取得先
- e-Taxでの取得・申請対応可否
- 法人用様式との違い(個人 vs 法人)
- 記入前に確認すべきこと(帳簿方式・事業内容など)
- フローチャートで見る申請手順
- 納税地・氏名・屋号・連絡先
- 所得の種類・事業所・資産の所在地
- 簿記方式・備付帳簿名の選択
- 取消し・取りやめの有無、相続承継欄の記載
- 開業日記入欄(1月16日以降開始のケース等)
- 関与税理士や特記事項欄の記入
- フリーランス・個人事業主の記入例
- 不動産所得を伴う人の場合の記入例
- 法人版・小規模企業版の記入例(参考)
- 窓口提出・郵送・e-Tax提出の違いと注意点
- 控えの取り方・保存方法
- 承認・不承認の判断基準・通知の流れ
- 項目の記入漏れ・誤記例
- よく見落とされる項目(簿記方式、開業日、相続欄等)
- 提出後に修正ができるか?対応方法
- チェックリスト
- 業種別の注意点(飲食・オンライン・不動産等)
- 開業と同時に出すか、後から出すか
- 青色申告取りやめや取消し経験がある場合の注意
- よくある質問への回答集
- チェックリスト形式で振り返る
- 最後の注意点とアドバイス
はじめに:青色申告承認申請書とは何か
「確定申告の時期になると、青色申告とか白色申告とか聞くけど、正直よく分からない…」そんな風に感じていませんか?
実は、私も会社員を辞めて開業届を出したとき、同じ疑問を抱えていました。事業主として独立したばかりの頃は、帳簿や記帳義務といった言葉だけで頭がいっぱいになり、「難しそうだし、白色申告でいいか」と思ったこともあったんです。
でも後から知ったんです。青色申告を選ぶかどうかで、所得税の負担が大きく変わるということを。
特に 65万円控除 や 10万円控除 といったメリットは、事業所得や不動産所得を得ている人にとって大きな節税につながります。
ここではまず、「青色申告承認申請書とは何か?」を、あなたと一緒に整理していきましょう。
青色申告制度のメリットと必要性
青色申告の一番の魅力は、やっぱり 控除額の大きさ。
白色申告では基本的に控除はありませんが、青色申告なら条件を満たせば 65万円控除 が受けられます。これは「複式簿記で帳簿をつけ、電子申告(e-Tax)で提出」する人向けの大きな特典です。
一方で、「複式簿記は難しいな…」という人でも、簡易簿記による 10万円控除 が選べます。どちらにしても、青色申告は 白色申告に比べて節税効果が高い のが特徴です。
さらに、青色申告では以下のような特典もあります。
- 赤字を3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できる
- 家族への給与を「専従者給与」として経費にできる
- 不動産所得・山林所得にも対応可能
「事業主として利益を守りたい」「税金を抑えて事業に再投資したい」──そう思うなら、青色申告は欠かせない選択肢です。
いつまでに出すべきか?提出期限のルール
「じゃあ、青色申告をやりたい!…でもいつまでに申請すればいいの?」
これもよくある疑問ですよね。
実は、青色申告をするには 事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出 しなければいけません。提出先は事業主の納税地を管轄する税務署です。
提出期限は次のように決まっています。
- 新しく事業を始めた場合:開業日から2か月以内
- すでに事業をしている場合:青色申告を始めたい年の 3月15日まで
つまり、たとえば1月に開業届を出したなら、3月までに青色申告承認申請書を提出しないと、その年の青色申告はできません。
私も一度、うっかり提出期限を逃してしまい、結局その年は白色申告をする羽目になりました。あのときの悔しさは今でも忘れません…。
だからこそ、あなたには同じ失敗をしてほしくないんです。提出方法は 窓口提出・郵送提出・e-Taxによる電子申告 のいずれかでOK。どれでも構いませんが、控えをきちんと取っておくことが大切です。
期限を守って提出できれば、国税庁から承認通知が届き、晴れて青色申告デビューできます。
その瞬間から、節税メリットを活かしつつ、自信を持って事業を進められるはずです。
青色申告承認申請書の様式と入手方法
「青色申告が有利なのは分かった。でも、その申請書ってどこで手に入れるの?」
私も最初、そう思っていました。税務署に行かないとダメなのか、それともネットでダウンロードできるのか…。調べてみると意外にシンプルで、安心したのを覚えています。
ここでは、青色申告承認申請書の 入手方法・申請書様式の違い・e-Tax対応 について、一緒に整理していきましょう。
国税庁公式様式と最新版の取得先
青色申告承認申請書は、国税庁の公式サイトで最新版をダウンロードできます。
「青色申告承認申請書 PDF」と検索すればすぐに出てきますし、書き方の記入例も国税庁が公開しているので便利です。
もちろん、最寄りの 税務署窓口 でも紙の様式をもらえます。開業届を提出するタイミングで一緒に渡されることも多いです。
私は昔、開業届と一緒に税務署で申請書をもらったのですが、最新版を探すならやはり国税庁のホームページが安心。古い様式を使うと不備になる可能性もあるので、必ず最新版を入手しましょう。
e-Taxでの取得・申請対応可否
「紙は面倒だから、全部オンラインでできないの?」と思う方も多いでしょう。
実は、e-Tax(電子申告) を使えば、青色申告承認申請書もオンラインで提出できます。
- 申請書様式をe-Tax上で入力・送信
- データはそのまま税務署に届く
- 控え(申請控え)も電子保存可能
私は一度、郵送提出で「到着が間に合ったか不安」になった経験があります。その点、e-Taxなら送信完了の記録が残るので安心感が段違いです。
もちろん、最初は「マイナンバーカードやICカードリーダーの準備が大変…」と感じるかもしれません。でも一度環境を整えれば、確定申告本番もスムーズになるので、個人的にはおすすめです。
法人用様式との違い(個人 vs 法人)
ここで気をつけたいのが、個人用と法人用の様式が別 だということ。
- 個人事業主向け:「所得税の青色申告承認申請書」
- 法人向け:「青色申告の承認申請書(法人税用)」
私の知り合いが、法人設立後に間違って個人用の申請書を出してしまい、税務署から連絡がきたことがあります。
事業所得・不動産所得・山林所得を扱う個人事業主なのか、法人として法人税を申告するのかによって、提出書類が違うので要注意です。
特にこれから開業する人は「開業届」とセットで個人用の様式を出すのが一般的です。法人設立予定の人は、法人登記後に法人用の様式を準備しましょう。
書き方ガイド:全体の流れと準備
「青色申告承認申請書を入手したけど、どこから手をつければいいの?」
最初にこの書類を見たとき、私は正直なところ「役所の書類ってやっぱり難しいな…」と感じました。
でも実際に一つひとつ進めていくと、「意外とシンプルなんやな」と思えるようになります。
ここでは、申請書を書く前に押さえておきたい準備と、全体の流れを整理していきましょう。
記入前に確認すべきこと(帳簿方式・事業内容など)
青色申告の大きな特徴は「帳簿をきちんとつける」こと。
そのため、申請書を書く前に 帳簿方式をどうするか を決めておく必要があります。
- 複式簿記:65万円控除が狙える。正確に資産・負債・収益を記録できるが、やや難しい。
- 簡易簿記:10万円控除。シンプルな記録で済むが、控除額は少ない。
私は最初、複式簿記に挑戦しましたが、簿記の知識が乏しくて苦労しました。結局、会計ソフトを使って何とか乗り切りました。今は便利なソフトが多いので、安心してください。
また、申請書には「事業内容」や「所得の種類(事業所得、不動産所得、山林所得)」を書く欄もあります。
たとえば、飲食店なら「飲食業」、Webライターなら「原稿執筆業」といった感じで、自分の屋号や事業をどう表現するかをあらかじめ考えておくとスムーズです。
フローチャートで見る申請手順
青色申告承認申請書の手続きは、ざっくり言うと次の流れです。
- 申請書を入手(国税庁HP・税務署窓口・e-Tax)
- 記入内容を整理(屋号、事業所得、不動産所得、帳簿方式など)
- 申請書を記入
- 提出先の税務署を確認(納税地を管轄する税務署)
- 提出方法を選ぶ(窓口提出・郵送提出・e-Tax電子申告)
- 申請控えを保存(提出後の証拠として必須)
- 国税庁からの承認通知を待つ
このフローを頭に入れておくと、必要な作業が明確になり、「書き方で迷う」時間がぐっと減ります。
私は最初、書きながら「あ、屋号決めてなかった!」と慌ててしまいました。準備不足だと余計に時間がかかるので、先に整理しておくのがおすすめです。
各項目の記入ポイントと記入例
「申請書の全体の流れはわかった。でも、実際に各項目をどう書けばいいの?」
私も最初はそうでした。書類を前にすると、「納税地ってどこ?」「屋号は必須?」「開業日ってどの日?」と迷うんですよね。
ここからは、申請書の各項目をひとつずつ解説しながら、記入例も交えてご紹介します。あなたがスムーズに書き進められるように、具体的にイメージできる形で整理しました。
納税地・氏名・屋号・連絡先
- 納税地:原則は「住民票の住所」です。事業所を別に設けている場合は事業所所在地も記載できます。
- 氏名:住民票どおりにフルネームで記入。印鑑欄は認印でOK。
- 屋号:必須ではありませんが、開業届と一貫性を持たせましょう。たとえば「やないデザイン事務所」など。
- 連絡先:電話番号は日中つながる番号を。メールアドレスは不要です。
👉 記入例:「大阪市北区〇〇町1-1-1 柳井弘幸 屋号:やない企画」
所得の種類・事業所・資産の所在地
- 所得の種類:事業所得、不動産所得、山林所得のいずれか。フリーランスは「事業所得」が一般的。
- 事業所所在地:自宅兼事務所なら同じ住所でOK。
- 資産の所在地:不動産所得がある人は、不動産の住所を記載。
👉 記入例:「事業所得 事業所所在地:大阪市北区〇〇町1-1-1」
簿記方式・備付帳簿名の選択
- 簿記方式:複式簿記か簡易簿記を選びます。65万円控除を狙うなら複式簿記+e-Tax提出が必須。
- 備付帳簿名:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳など。会計ソフトを使う場合でも代表的な帳簿を列挙しておきましょう。
👉 記入例:「複式簿記 備付帳簿名:仕訳帳、総勘定元帳、経費帳」
取消し・取りやめの有無、相続承継欄の記載
- 取消し・取りやめ:過去に青色申告をやめた経験がある人は「あり」にチェック。なければ「なし」でOK。
- 相続承継欄:親の事業を引き継いだ場合にのみ記入。通常の開業時は空欄でOK。
👉 記入例:「取消し・取りやめ:なし 相続承継:該当なし」
開業日記入欄(1月16日以降開始のケース等)
開業日をいつにするかで提出期限も変わります。
- 1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2か月以内に提出
- 年初から事業をしている場合 → その年の3月15日まで
👉 記入例:「令和7年2月1日開業」
私は一度「開業届の日付」と「実際に仕事を始めた日」がずれて混乱しました。基本は「最初の売上が発生した日」または「事業準備を本格的に開始した日」と考えるのが無難です。
関与税理士や特記事項欄の記入
- 関与税理士:税理士にお願いしている場合は記入。自分でやるなら空欄でOK。
- 特記事項:特に伝えたいことがある場合のみ記入(例:前年は白色申告だったが、今年から青色に切り替えるなど)。
👉 記入例:「関与税理士:山田太郎税理士事務所 特記事項:前年は白色申告」
こうして見ると、一見ややこしそうに見える項目も「自分の状況に当てはめればシンプル」だと分かりますよね。
一つずつ丁寧に書いていけば、必ず完成します。
記入済み見本:具体例+解説付き
「実際にどう書けばいいのか、完成形を見たい!」
──そんな気持ち、よく分かります。私も最初は、国税庁の申請書様式を開いて「ここって何書けばいいんや?」と手が止まってしまいました。
そこで、この章では フリーランス・不動産所得がある人・法人 の3パターンを取り上げ、実際の記入例を示しながら解説します。
フリーランス・個人事業主の記入例
たとえば、Webライターとして独立したケースを見てみましょう。
- 納税地:東京都新宿区〇〇町
- 氏名:山田花子
- 屋号:ハナコライティング
- 所得の種類:事業所得
- 事業所所在地:自宅兼事務所
- 簿記方式:複式簿記
- 備付帳簿名:仕訳帳、総勘定元帳、経費帳
- 開業日:令和7年1月10日
👉 ポイント:
この場合、複式簿記+e-Tax提出で65万円控除が狙えます。会計ソフトを導入すれば初心者でも問題ありません。
不動産所得を伴う人の場合の記入例
次に、不動産収入があるケースです。たとえば「サラリーマンをしながらアパート経営をしている」人を想定します。
- 納税地:大阪市北区〇〇町
- 氏名:佐藤一郎
- 所得の種類:不動産所得
- 資産の所在地:大阪府吹田市〇〇マンション
- 簿記方式:簡易簿記
- 備付帳簿名:現金出納帳、家賃収入帳、経費帳
- 開業日:令和7年4月1日
👉 ポイント:
不動産所得では、経費管理や修繕費の記帳が重要になります。大規模経営でなければ、簡易簿記+10万円控除でも十分。ただし、長期的に規模を拡大するなら複式簿記をおすすめします。
法人版・小規模企業版の記入例(参考)
最後に、法人の場合を見ておきましょう。
- 納税地:名古屋市中区〇〇町
- 法人名:株式会社グロース企画
- 代表者:田中太郎
- 所得の種類:法人税の青色申告
- 事業内容:マーケティングコンサルティング
- 簿記方式:複式簿記(法人は必須)
- 開業日:令和7年5月1日設立
👉 ポイント:
法人は基本的に複式簿記が必須。法人税・消費税の申告も絡むので、税理士に依頼するケースが多いです。
こうして具体的な記入例を見ると、「自分の場合はどのパターンに当てはまるのか」がイメージしやすくなりますよね。
最初は不安でも、こうした見本を参考にすれば必ず書き上げられます。
提出方法と提出後の流れ
「書類を書き終えたけど、どうやって提出すればいいの?」
──ここで立ち止まる人も多いんですよね。私も最初は「税務署に持って行かないといけないのかな?郵送でも大丈夫?」と迷いました。
実は青色申告承認申請書の提出方法は、窓口提出・郵送提出・e-Tax(電子申告) の3つから選べます。さらに、提出後にどんな流れで承認通知が届くのかも理解しておくと安心です。
窓口提出・郵送・e-Tax提出の違いと注意点
- 窓口提出
税務署に直接持参する方法。職員がチェックしてくれるので安心感があります。ただし、確定申告時期(2月〜3月)は混雑するので要注意。 - 郵送提出
税務署に書類を郵送する方法。返信用封筒を同封しておけば「申請控え」に受付印を押して返送してもらえます。私はこの方法をよく使います。 - e-Tax(電子申告)
インターネットで24時間提出可能。マイナンバーカードやICカードリーダーが必要ですが、一度環境を整えれば今後の確定申告も楽になります。送信記録が残るので安心です。
👉 ポイント:
どの方法でも有効ですが、必ず控えを残すこと が大事です。
控えの取り方・保存方法
「控えって何?」と思うかもしれません。控えとは、提出した申請書のコピーに受付印(もしくは送信記録)がついたもののこと。
- 窓口提出 → コピーを持参して受付印を押してもらう
- 郵送提出 → 返信用封筒+切手を同封して返送してもらう
- e-Tax提出 → 電子送信後の受信通知を保存する
私も一度「控えを取らずに提出」してしまい、税務署に確認する羽目になったことがあります…。後で確定申告するときや、金融機関に提出するときに必要になる場合があるので、必ず保存しておきましょう。
承認・不承認の判断基準・通知の流れ
申請書を提出すると、税務署で内容が確認されます。
- 問題がなければ承認通知が届く(通常は提出から1〜2か月後)
- 不備や記入漏れがあると修正依頼が来る
- 過去に取り消し経験がある場合、承認されないこともあります
ただ、基本的には「期限を守って、正しく記入して提出」していれば、ほとんど承認されます。
通知は郵送で届くことが多いですが、e-Taxなら電子通知で確認できます。承認通知が来れば、その年から青色申告が可能に。
👉 つまり、提出が完了した時点で大きなハードルはクリアしたことになります。
こうして提出方法や流れを知っておくと、「ちゃんと受理されるかな?」という不安がぐっと減ります。
あとは、控えを大切に保管し、承認通知を待つだけです。
よくある記載ミス・失敗例とチェックリスト
「やっと書き終えた!…でも、このまま提出して大丈夫?」
初めて申請書を書くとき、私はこの不安で何度も書類を見直しました。実際、青色申告承認申請書はシンプルに見えて、意外と小さなミスをしがちなんです。
ここでは、よくある記入ミスや提出後の対応を整理して、あなたが安心して出せるようにチェックリストを用意しました。
項目の記入漏れ・誤記例
最も多いのが、空欄のまま提出してしまう ケースです。
- 「屋号」を空欄にして出した(→任意項目なので大丈夫だが、開業届と統一しておくとベター)
- 「簿記方式」を未記入にした(→青色申告の種類が決まらず不備になる)
- 「開業日」を忘れた(→提出期限の判定に必要)
👉 ポイントは、「提出先の税務署があなたの状況を正しく判断できるか?」を意識すること。
よく見落とされる項目(簿記方式、開業日、相続欄等)
私がやってしまったのは、「相続承継」の欄を空欄にして提出したこと。
通常の開業なら空欄でOKなのですが、税務署から「相続承継はなしでよろしいですか?」と確認の電話がありました。
特に見落としやすいのは次の項目です。
- 簿記方式:複式簿記か簡易簿記か必ず選ぶ
- 開業日:日付を正確に(迷ったら最初の売上日)
- 取消し・相続承継欄:特に該当がないなら「なし」と記入しておくと親切
提出後に修正ができるか?対応方法
「もう提出しちゃったけど、間違えてた!」──大丈夫です。
申請書は提出後でも修正できます。
- 軽微なミス(電話番号、屋号の誤字など) → 税務署に連絡して訂正届を出す
- 重大なミス(簿記方式の誤記、開業日の間違いなど) → 新たに申請書を出し直す
私も一度、提出後に「屋号を変えたい」と思ったことがありました。そのときは税務署に相談し、訂正で済みました。焦らず、必ず税務署に相談するのが一番です。
チェックリスト
提出前に、次のポイントを確認しましょう。
✅ 納税地・氏名・屋号は記入したか
✅ 所得の種類(事業所得、不動産所得、山林所得)は間違っていないか
✅ 開業日は正しいか
✅ 簿記方式を選んだか(複式簿記 or 簡易簿記)
✅ 相続承継・取消し欄に「なし」と記入したか
✅ 提出方法(窓口・郵送・e-Tax)を決めているか
✅ 控えを残す準備をしたか
このチェックをすれば、大きな失敗は防げます。
「不備で突き返されたらどうしよう…」という不安もなくなり、自信を持って提出できますよ。
ケース別注意点・Q&A
「自分のケースだと、どう書けばいいんだろう?」
──実は、青色申告承認申請書は 業種やタイミングによって注意点が違う んです。私も独立当初、「開業届と一緒に出すのが正解?それとも後からでも大丈夫?」と悩みました。
ここでは、よくあるケース別の注意点と、Q&A形式で疑問を解決していきましょう。
業種別の注意点(飲食・オンライン・不動産等)
- 飲食業
店舗を構える場合は「事業所所在地」を忘れずに。複数店舗を持つなら、本店を中心に記載します。 - オンラインビジネス(Webライター、デザイナー、YouTuberなど)
自宅を事務所にする人が多いため、「住所=事業所所在地」でOK。屋号を付けると信頼感も出ます。 - 不動産業
不動産所得を申告する場合、「資産の所在地」を記載するのを忘れがち。家賃収入や修繕費の管理もあるため、帳簿付けは特に重要です。
👉 業種によって「抜けやすい項目」があるので要注意。
開業と同時に出すか、後から出すか
理想は、開業届と同時に青色申告承認申請書を出す こと。
この場合、開業日からスムーズに青色申告ができます。
ただし後からでも大丈夫で、ルールは以下のとおり:
- 開業後 → 2か月以内
- 既に事業をしている人 → その年の3月15日まで
私は一度、開業から3か月以上経って提出したため、その年は白色申告になってしまいました…。提出期限を守るのが何より大切です。
青色申告取りやめや取消し経験がある場合の注意
過去に「青色申告の取りやめ」や「税務署からの取消し」があった人は注意が必要です。
- 税務署の判断で、一定期間は再申請できない場合がある
- 申請書に「取りやめ・取消し経験あり」と記入する必要あり
「以前に取消し経験があるから承認されないのでは?」と不安になる方もいますが、きちんと申請し直せば再承認されるケースも多いです。まずは正直に記入しましょう。
よくある質問への回答集
- Q:屋号は必須ですか?
→ いいえ。空欄でも申請できます。ただし開業届と揃えておくとスムーズです。 - Q:白色申告から青色申告に切り替えるときも同じ書類ですか?
→ はい。同じ「青色申告承認申請書」を提出します。 - Q:郵送提出のとき、控えはどうやって返してもらえますか?
→ 返信用封筒と切手を同封すれば、受付印を押した控えが返送されます。 - Q:税理士にお願いしている場合は、記入しなくてもいいですか?
→ 関与税理士欄に記載するのが原則です。省略すると税務署から確認が入ることもあります。
こうしたケース別の知識を押さえておけば、自分に合った形でスムーズに申請できます。
「これで大丈夫かな?」と不安になったときも、答えを知っているだけで安心できますよ。
まとめ:申請成功のためのポイント総まとめ
ここまで一緒に見てきて、「青色申告承認申請書って、思ったよりもシンプルやな」と感じてもらえたのではないでしょうか。
私自身も最初は「難しそう…」と身構えていましたが、実際にやってみると、ポイントさえ押さえればスムーズに提出できることが分かりました。
最後に、申請を成功させるための大事なポイントを整理しておきましょう。
チェックリスト形式で振り返る
✅ 青色申告のメリット(65万円控除/10万円控除、赤字繰越、専従者給与など)を理解したか
✅ 提出期限を確認したか(開業後2か月以内 or その年の3月15日まで)
✅ 申請書の最新版を 国税庁HP・税務署窓口・e-Tax で入手したか
✅ 簿記方式(複式簿記 or 簡易簿記)を決めたか
✅ 所得の種類(事業所得・不動産所得・山林所得)を正しく選んだか
✅ 控えの保存方法を準備したか(窓口・郵送・電子申告)
✅ 記入ミスや空欄がないかチェックしたか
最後の注意点とアドバイス
青色申告の承認は「期限を守って、正しく申請する」ことさえできれば、ほぼ間違いなく承認されます。
逆に、うっかり期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告しかできなくなり、控除を受けられないという大きな損失につながります。
私も一度、提出が遅れて白色申告になった経験がありますが、そのときは数十万円の節税を逃しました…。だからこそ声を大にして言いたいんです。
👉 「早めに出す」これが一番の秘訣です。
あなたが今日、このページを読んでいるということは、すでに一歩を踏み出している証拠です。
もし少し不安があっても大丈夫。誰だって最初は迷うものです。
どうか自信を持って申請を済ませ、来年の確定申告で「やってよかった!」という実感を味わってください。
私も同じように失敗や試行錯誤を経てきたからこそ、あなたの挑戦を心から応援しています。